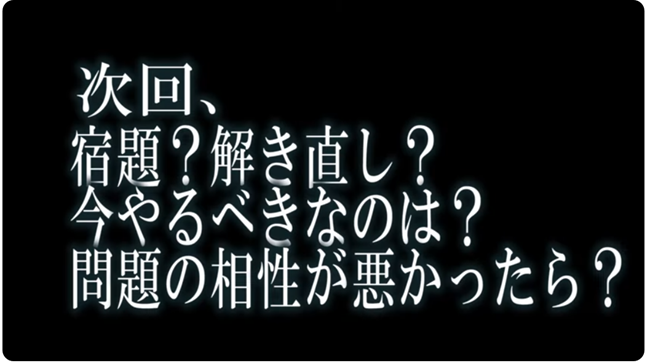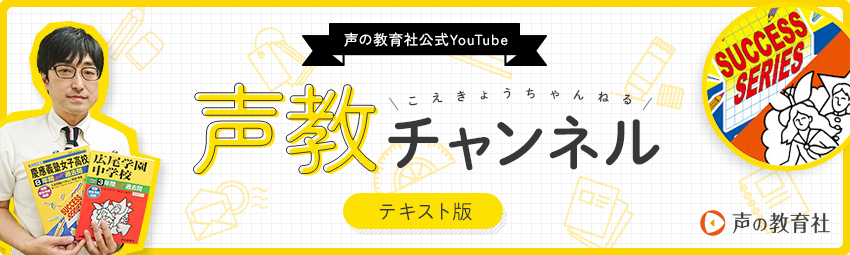帰ってきた声教保護者会2025-2026②「受験勉強 今やっていることの意味は?私学のイベントでモチベーションアップ!?」
出典:声教チャンネル(声の教育社)
記事:metasc
前回の声教保護者会の続きで、「受験生が今やっていることの意味合いについて」のお話です。
※前回については『帰ってきた声教保護者会2025-2026 10月①「あの夏期講習はなんだったのか…!過去問や模試の成績に一喜一憂゚(;´д`)」~前編~』をご確認ください。
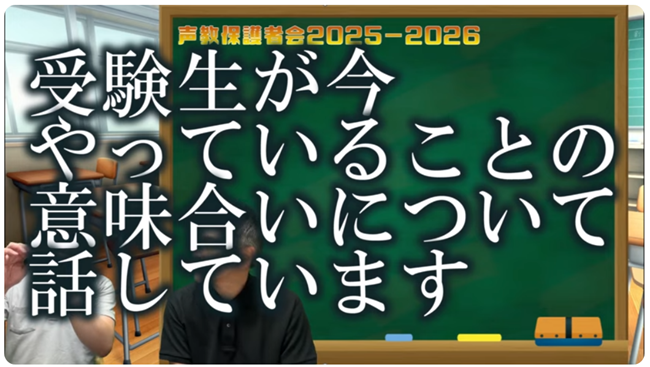
▼今やっていることの意味
前回のお話では、夏期講習は…「苦手や穴を見つけるための期間」である、というお話をしました。
そして、2学期以降はその見つけた課題をしっかり埋めていく時期になります。
つまり!
・「入試で使える知識や技を増やしていくこと」
・「必要な場面でそれを使いこなせるように訓練していくこと」
がポイントです。
そのときに大きなツールとなるのが、塾の授業に加えて「過去問」と「模試」の2つです。
どちらも大切ですが、この2つは性質がまったく異なります。
□過去問
過去問は、たとえば東京・神奈川なら2月1日、埼玉は1月10日ごろ、千葉は1月20日ごろから始まる入試本番と直結しています。
つまり、過去問というのは「ゴール(入試)」そのものを想定した問題です。
ですから、最初のうちは頑張って解いても、なかなか点数が取れないのが普通です。
さらに、学校ごとに「こんな思考を持った生徒に来てほしい」というメッセージが問題に込められており、模試とはまったく違う特徴を持っています。
たとえば、算数が得意だと思っていても、学校によってはまったく歯が立たないこともあります。
でも、解説を読んでみると「得意な〇〇算で解けたんだ!」と気づくこともありますよね。
そんな発見の積み重ねこそが、過去問演習の大きな価値なのです。
また、過去問は過去の合格者たちの“本番の実力”との比較になります。
ですので、9月の段階で2月本番の入試問題の合格者最低点を超えるというのは、とんでもなく、本当にすごいことなのです!
塾によって過去問は…
・「第一志望校から過去問を始めよう」
・「まずは安全校(堅実校)から取り組もう」
と方針は様々あります。
どちらにせよ、最初は思うように点が取れないことが多いです。
「この学校は比較的安全かな」と思っていても、正答が半分ちょっと、なんてこともよくあります。
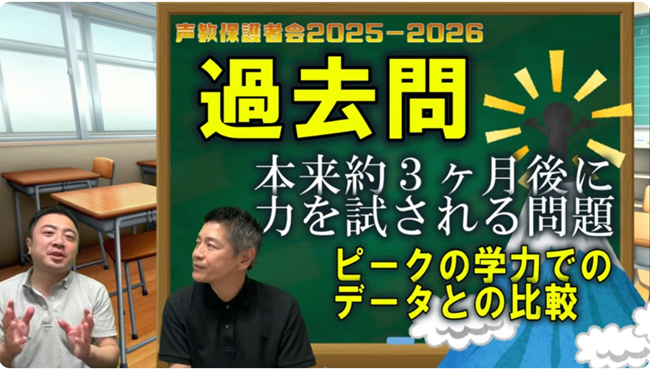
□模試
一方で模試は、「今年のライバルたち」との比較です。
過去問が“先輩たち”との比較
模試は“今の仲間たち”との勝負
になります。
模試の偏差値は、今の段階ではみんな点が取りにくい状況での比較なので、志望校の偏差値自体は大きく変わらないように見えるかもしれません。
でも、「過去問の合格者最低点にはまだ届かない」ということは本当によくある話です。
だからこそ、模試の結果に一喜一憂せず、「今の自分を知るチャンス」として受け止めていくことが大切です。
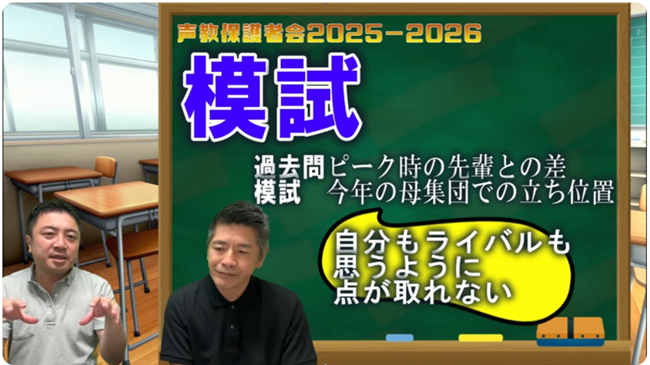
▼保護者の姿勢
□スケジュール
まず大人が忘れてはいけないのは、「受験生とはいえ、子どもたちはまだ小学生である」ということです。
近年は気候の変化もあり、運動会の時期が9月ではなく、少し涼しくなった10月に行われる学校も増えてきました。そのため、受験生によっては2学期に運動会があったり、もう終わっていたりと、学校によってさまざまです。また、修学旅行が秋にある学校も多いですよね。
どちらの行事も、せっかくなら中途半端にではなく、一生懸命に取り組んでほしいと思います。
・応援団として声を張ること
・競技で全力を出すこと
これらは小学生として大切な経験です。
ですから、「受験生だから」といって学校生活を控えめにするのではなく、小学生らしい頑張りも忘れずにいてほしいですね。
とはいえ、もちろん受験生でもあります。
勉強も生活も気を抜かず、バランスよく取り組んでいくことが大切です。
この時期は、
・学校行事
・中学校の説明会やオープンキャンパス
なども増え、ご家庭によってはスケジュールの調整が本当に大変だと思います。
塾によっては日曜日に特訓が入ることもあり、スケジュールはどんどん詰まっていきます。
過去問も、1年分を4教科解くだけで約4時間。さらに丸付けや解き直しを含めると、6時間ほどかかります。
それを塾の授業や宿題と両立するのは、なかなかのハードスケジュールですよね。
ご家庭によっては土日に…
・まとめて過去問を解く
・保護者の方と一緒に復習時間を取る
など、工夫されていると思います。
どうしても忙しくなりがちな時期ですが、無理のないスケジュールで一歩ずつ進めていきましょう。
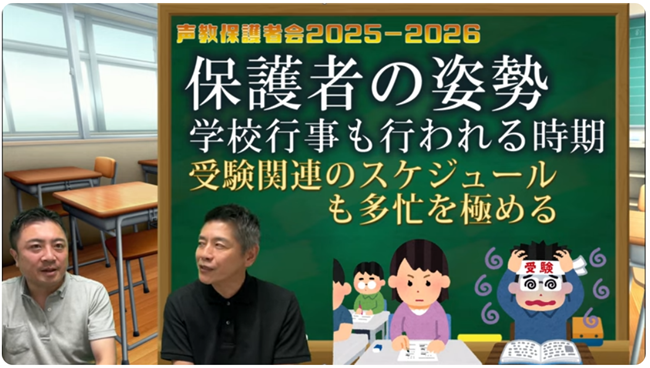
□受験生の体調管理
この時期は季節の変わり目でもあり、気温差や気候の変化で体調を崩しやすくなります。
だからこそ、保護者の皆さまにぜひお願いしたいのが体調管理です。
中学受験をしているとはいえ、まだ小学生ですので、保護者による体調管理が非常に大切です。
そして身体面だけでなく、心のケアも同じくらい大切です。
・体調が悪いと気持ちも沈みやすくなる
・メンタルが不安定だと体調も崩しやすくなる
という関係が成り立ちます。
小学生はとても繊細で、「不安」「緊張」「プレッシャー」といった気持ちが、そのまま体調に表れることもあります。
まるで“ちょっと嫌なことがあると熱を出してしまう”という特技を持っているようなものです。
だからこそ、心と体の両面をやさしく見守りながら、安心して頑張れる環境を整えていきましょう。
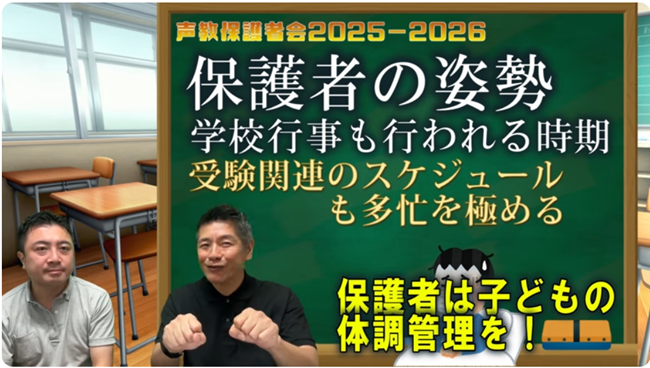
□保護者の一喜一憂
模試の結果についても、ここはとても大事なポイントです。
9月・10月の模試で思うように結果が出ないと、「このままで大丈夫だろうか…」と不安になる保護者の方も多いと思います。
ただ、その焦りや不安を感情に乗せてしまうと、そのままお子さんに伝わってしまい余計にプレッシャーを感じさせてしまうことがあります。
ですので、ぜひ冷静に受け止める姿勢を大切にしてください。
結果が出なかったときこそ、塾の先生に相談してみましょう。
・「少し厳しく叱咤激励した方がいいタイプ」
・「模試で分かって良かったね、本番はこれからだよと励ました方がいいタイプ」
なのか、お子さんの性格や状況に合わせて声をかけることが大切です。
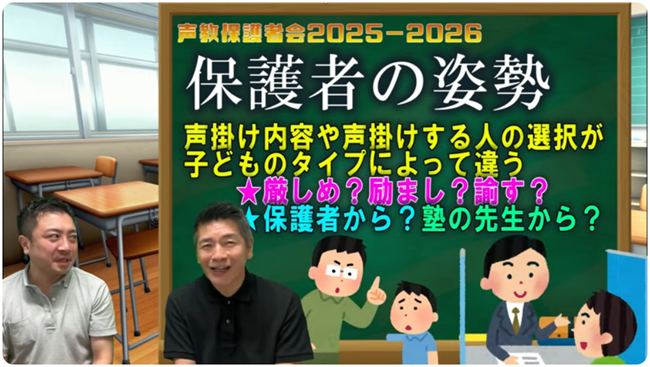
▼10月以降の学校イベント
6年生のこの時期は、中学校でも
・入試説明会
・文化祭
・オープンキャンパス
などのイベントがたくさんありますね。
「忙しいのに行くべきなのかな?」と迷う方も多いと思いますが、結論から言えば、行ってみる価値は大いにあります。
もし最近お子さんの成績が思うように伸びず、少し気持ちが沈んでいる、モチベーションが下がっている…という状況なら、
気分転換も兼ねて一緒に参加してみるのはとても良いことです。
学校の雰囲気に触れて「よし、もう一度頑張ろう!」と気持ちを立て直すきっかけになることも多いです。
また、一般的な説明会だけでなく、6年生対象の入試説明会もあります。
保護者の方は情報収集の意味でも、ぜひ積極的に参加してみてください。
文化祭やオープンキャンパスも説明会も同様で、お子さんにとっては“目で見て感じるモチベーションアップの場”になります。
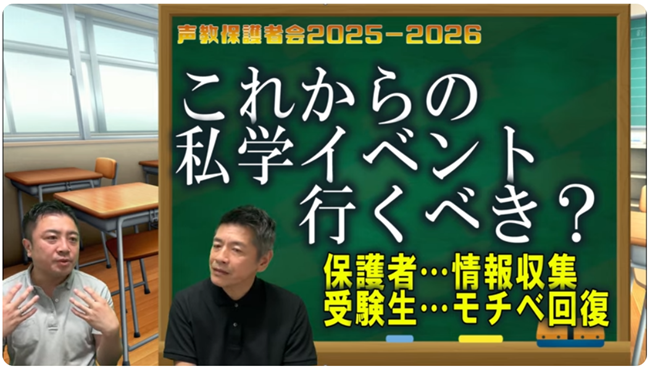
さらに10月から11月にかけては、模試や過去問の結果を見て「受験、続けていいのかな…」「志望校を下げようかな…」と悩む保護者の方が増える時期です。
そんなときこそ、説明会に参加してみてください。
実際に学校の様子を見て…
「やっぱりこの学校で6年間を過ごしてほしいな」
と改めて感じることで、保護者の方のモチベーションもぐっと上がります。
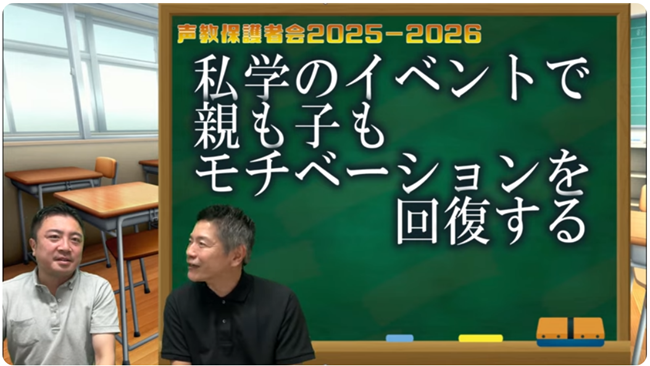
特におすすめしたいのが、在校生と直接話ができるイベントです。
最近は…
・生徒さんが案内をしてくれる
・個別に質問に答えてくれる
学校が本当に増えています。
・「この教科はどうしていましたか?」
・「受験のときは大変でしたか?」
などと聞くと、
「僕はこうしました」「私はこう乗り越えました」と、リアルな体験談を聞かせてくれることもあります。
生徒さんたちは、「自分の学校の良さを伝えたい!」という気持ちでいっぱいです。
その素直で等身大の言葉から、たくさんのヒントが得られます。
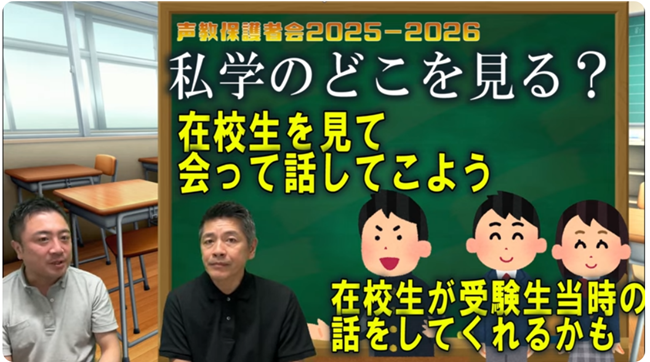
しかも最近では、広報委員の生徒たちが先生の“台本”なしで話してくれることも多く、
本音の学校生活が垣間見えるのも魅力的ですね。
先生とは違う視点で語られる“生の声”には、とても新鮮な発見があります。
(※「声教ツアーズ」でも、生徒の広報係による学校案内が数多く紹介されています。)

持論ですが、
「今のわが子に合う学校」=「未熟なわが子に合う学校」
となってしまい、なかなかそこから先の、わが子の伸び代が見えにくいと思います。「なぜなら、今の子どもはまだ発展途上で、これから大きく伸びていく存在だからです。
学校見学に行くと、先輩たちの姿を見て「うちの子もこんな風に成長してほしい」と思える瞬間がありますよね。
そこに“未来のロールモデル”がたくさんいます。
しかも、いろんなタイプの先輩がいるので、「うちの子に近いタイプの子も頑張っている!」と感じられることも多いです。
そうした姿を目にすることで、保護者の方の気持ちも自然と明るくなり、「もう少し頑張ろう」と前向きなエネルギーが戻ってくるものです。
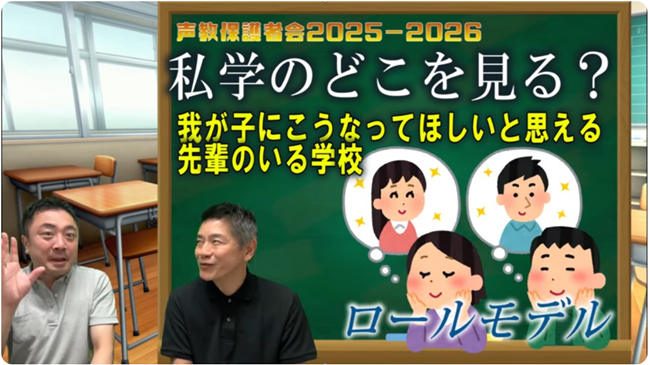
▼次回予告
10月を過ぎると、どうしてもモヤモヤした不安がたまりやすくなります。
そして11月には、そのモヤモヤがさらに大きくなっていく時期です。
次回は、
・宿題や解き直しの進め方
・11月にやるべきこと
・過去問との相性が悪かった場合の対応法
についてお話しします。
少しでも皆さんの受験生活が前向きで充実したものになるよう、次回もぜひ参考にしてくださいね。